
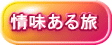

空海 0番札所 2017年 7月31日
空海が、遣唐使として中国に向かったのは、31歳の時である。
西暦804年のこと、当時の中国は756年に安禄山の乱が発生し、かつてのような繁栄はない状況のことです。
遣唐使が菅原道真の進言で廃止になるのが894年ですから、衰えたとは言え、まだまだ中国から学ぶことの多く
あった時代でした。
26年ぶりに派遣される遣唐使船には、空海と並び称される最澄も一緒に行っています。ただその処遇は、まったく
異なったものでした。
最澄は、空海よりも8歳くらい年長で、当時の桓武天皇に見込まれ国を代表する留学僧として当に通訳付きで最高の
処遇で1年間の限定で長安に赴いています。

一方の空海は、私費留学の僧として、まったくの無名僧で、留学期間も20年間の予定という当時でいえば帰って
来られる見込みもないような留学でした。
最澄が若いころから比叡山に入りエリート僧としての道を歩んだの対して、空海はもともとは裕福な家で、大学で
儒教を学びましたが次第に仏教に目覚め大日教を学びますが日本で学べる限界を感じ、何としても本物を学びたい
という思いから中国へ私費留学を決意するのです。
この遣唐使は、4隻の船で構成され第1船目に空海、第2船目に最澄が乗っていたといいます。そして、第3船目、
第4船目は途中で難破してしまいます。こうした流れをみても2人の背負っていた宿命というのを感じさせられます。
2人は、中国に入り最澄は1年の留学生活を予定通り終わらせます。
空海は長安で、運命的な出会いを迎えます。唐の国師で正統な密教を受け継いだ僧「恵果」に会うのです。
恵果は空海に会うなり「我先より汝の来れるを知れり、相待つこと久し」といったといいます。
そして密教の正統を受け継ぎ伝法阿闍梨位の灌頂を受けて真言密教の第八祖となります。その灌頂名が遍照金剛です。
この六か月後恵果は亡くなっています。二年余りを長安で過ごし、その当時の最高の教えを集めて空海は帰国の途に
つきます。

ただ、20年の命令で来ていますから、簡単に都に戻ることはできません。
九州で3年余りを過ごし、真言密教を全国に広めるので都に戻る許しを請います。
都に戻った空海が持ち帰った経典をみて、密教のすべてが日本にもたらされたと最澄はいいます。

空海は、桓武天皇の後を継いだ嵯峨天皇に認められ、京都東寺を拠点に真言宗を広めていきます。
最澄は、比叡山で天台宗を広めて行くわけです。
二人の布教は対照的です、最澄は国の代表、模範としての宗教布教に取り組みます。
空海は、人々の中に入り込み布教を行っていきます。空海の言葉に「物事の興廃は人による」があります。
人々の心こそが本当に大事と説いています。その後を見れば二人の志が見えてきます。
比叡山からはその後、浄土宗を開いた法然、日蓮宗を開いた日蓮、曹洞宗の道元が出ています。
今の日本の主だった宗派が生まれています。
一方の空海の方は、弘法大師とおくり名されて、弘法さんと民衆から慕われる存在になっていきます。
高野山の奥の院に行きますと、弘法大師さんに守られて成仏したいと日本の有名な人々のお墓が数多く立っています。
四国八十八か所巡りは弘法大師さんが修行された地として今でも多くの方が訪れる場所になっています。
そこで、空海が真言宗の奥義を恵果から伝授された場所こそは、八十八か所巡りの起点と考えてよいと考えて、
0番札所としました。
今の西安の郊外、地下鉄の駅の青龍寺という駅から歩いて10分位のところにこのお寺があります。
このお寺を見ると、素朴で日本の高野山や東寺と比べるととても質素な佇まい。1200年の歳月がこれほどまでに
お寺というものをそして宗教というものを隔ててしまったことを実感できます。
見ていると、つい先日まで空海がここで修行していたような錯覚に陥ります。このお寺に佇んでいると、
命がけで修行のためにはるばる日本からやってきた空海の気迫がいまでもこのお寺の中に残っているのを
感じ取ることができます。
